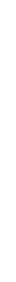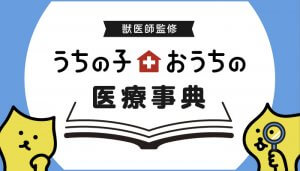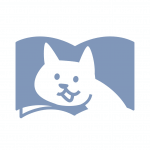アイペット損保が、自社のペット保険のご契約者さまに実施した「飼い方アンケート」(※調査概要参照)の結果について、2020年から2022年にかけて変化した項目をみると、コロナ禍での生活スタイルの変化が、愛猫との飼い方にも影響をもたらしていることがわかりました。本記事では、約80個の質問の中から「3か年で変化した項目」についてご紹介していきます。
ネコちゃんとの関係について
変化①「初めて猫を飼った人の割合が増えた」
「過去にネコちゃんを飼育した事はありますか?」という質問では、2022年は「はい」が69.4%(2020年「はい」83.5%→21年71.1%→22年69.4%)と飼育経験者の割合が年々低下し、初めてネコちゃんを飼った飼い主さんの割合が増えました。コロナ禍を機にこれまでペットを飼ったことの無いご家庭で、ネコちゃんをお迎えした方が増えたようです。

アイペット獣医師チームから一言
はじめてネコちゃんと一緒に生活される方は、その気まぐれさからコミュニケーションに悩むことがあるかもしれません。そんな時、ネコちゃんと一緒に楽しくチャレンジできる「コマンドトレーニング」に挑戦してみるのはいかがでしょうか?
変化②「うちの子は天才だと思う飼い主さんが増えている」
「うちの子は天才だと思いますか?」という質問では、「はい」と答えた方の割合が増えています(2020年34.8%→21年38.5%→22年39.3%)。愛猫と過ごす時間が長くなり、うちの子の意外な天才っぷりを発見できた場面に遭遇したのかもしれません。
獣医師チームから一言
天才ネコちゃんは明晰な頭脳と柔軟な体を使って、隠してあるものを見つけ出したり、入ってほしくない場所に入ったりしてしまうかもしれません。食べてはいけないものや触ると危険なものは、改めて置き場所をチェックしておきましょう。
変化③「甘やかしすぎていると感じている飼い主さんが増えている」
「あなたのネコちゃんに対する接し方で一番近いものをお選びください。」という質問では、「甘やかしすぎている」を選択した飼い主さんの割合がわずかながら増え続けています(2020年16.6%→21年17.1%→22年18.6%)

獣医師チームから一言
かわいいネコさまにデレデレになってしまうのは仕方のないことです。でも、おねだりされるがままにおやつをあげて肥満になってしまったり、嫌がるからといって日常ケアを何もしないのは、ネコさまのためにはなりません。心を鬼にして適度な我慢を教えることも、時には必要かもしれませんね。
予防・診察について
変化①「ノミダニの予防頻度で月1の割合が増えた」
「ノミダニに関する予防の頻度において最も近いものをお選びください」という質問では、月に1回を選択された人の割合が増えています(2020年の18.8%から2022年には26.2%)。月1回の投薬で、フィラリア予防とノミ・マダニ・おなかの虫の駆除ができるオールインワンタイプの方法が、普及している様子が窺われます。
|
月に1回 |
2~3ヵ月に1回 |
年に1回 |
出かけるときだけ |
していない |
|
|
2022年 |
26.2% |
11.8% |
12.6% |
1.4% |
48.0% |
|
2021年 |
26.0% |
9.9% |
13.3% |
1.7% |
49.1% |
|
2020年 |
18.8% |
13.1% |
17.4% |
1.4% |
49.4% |
獣医師チームから一言
うちの子は完全室内飼育だから関係ない!と思う方もいるかもしれませんが、外に出かけた飼い主さんがノミやマダニをおうちに持ち込んでしまう可能性は十分にあります。おうちの中は一年中快適な環境で、ノミやマダニの繁殖力は驚異的です。気を抜かずに、しっかり予防を行いましょう!
変化②「フィラリアの予防をする人が増えた」
変化①の結果からも窺えますが、「フィラリアの予防をしていますか?」という質問では、2020年で「はい」は25.%→21年31.2%→22年48.2%と、フィラリア予防をされる方の割合が急上昇しています。その一方で「フィラリアに関して感染のリスクはどれくらい感じていますか?」という質問では、予防する割合が増加した影響で、感染リスクをあまり感じない割合が増えたようです。(「感染リスクをあまり感じていない」2020年25.2%→21年31.4%→22年32.9%)

獣医師チームから一言
フィラリアの本来の宿主はワンちゃんなので、ネコちゃんは寄生されても、体の中でフィラリアが成虫まで成長しきらない場合も多いです。でも、ネコちゃんの場合は寄生する数が少ないために発見が難しかったり、気付いた時には重症化していることもあるため、ぜひ危機感を持って予防していただければと思います。
変化③「デンタルケアをする人が増えている」
「デンタルケアはどのくらいの頻度で行っていますか?」という質問では、「していない」と答えた方の割合が年々減少しています(2020年49.9%→21年45.2%→22年43.6%)
また「おうちでデンタルケアは必要だと思いますか?」という質問では、「はい」と答えた方の割合が年々増えており(2020年81.6%→21年83.1%→22年83.6%)、実際に歯磨きをしている方の割合以上に、意識の面では必要性を感じている方の割合が多くなっています。実際に歯磨き実行へのハードルがあるようです。

獣医師チームから一言
ネコちゃんはお口を触られるのを嫌がる子も多く、歯磨きのハードルが高いのも納得です。まずはガーゼなどで歯に触ることから始めて、徐々にステップアップしていきましょう!
「猫の歯」に関する記事もあわせてご一読ください。
□ 生え変わり:猫の歯、生え変わるのはいつぐらい?
□ 歯ぎしり:猫も歯ぎしりをするの?その原因とは?
□ 抜けた:猫の歯は抜けるの?折れることもあるの?
□ 歯磨きの仕方:猫の寿命を延ばす歯磨きの仕方って?
□ 歯磨き初心者:初心者からできる!上手な猫の歯磨き
□ 歯磨きのコツ:猫の歯磨きのコツとは?
□ 歯周病:猫の歯周病、症状や治療法とは?処置が遅れると、
□ 歯周病:歯が抜けてしまうことも!猫の歯周病とは
□ 人の歯との違い:人間の歯と、猫の歯の違いとは?
□ まとめ:ねこ飼いさんの基礎知識「ねこの歯」
変化④「健康診断を受診する人が増えている」
「健康診断をどのくらいの頻度で受診していますか?」という質問では、1年に1回以上健康診断を受診する人の割合が増えました(2020年56.7%→21年67.4%→22年68.5%)。健康診断で血液検査や画像検査を行うことで、隠れている不調の早期発見につながります。

獣医師チームから一言
健康診断は不調を発見するだけではなく、元気な時の状態を知っておくことや、健康であることを確認して安心感を得るという大事な意義があります。6歳頃までは1年に1回、7歳以降のシニア期は半年に1回を目安に受診できると良いですね。
うちの子の長生きのための「健康チェック」
□ 不調のサイン:おうちでできる猫ちゃんの健康チェック方法
□ 自宅で健診:自宅でできる猫の健康チェック
□ 猫の健康チェック:猫の健康状態を確認する方法とは?日常的、
□ 1日の活動量:猫の健康状態をチェック!
□ シニア猫の健康チェック:シニア猫の健康チェック方法とは?
□ 子猫の健康チェック:子猫の健康チェック方法とは?
□ ウンチの見極め:猫のうんちでできる健康チェック
食生活について
変化①「ごはんをあげる回数が増えた」
「ご飯は1日何回あげていますか?」という質問では、1日3回以上あげている割合が、2020年29.9%→21年35.6%→22年35.3%と増えています。在宅ワークの普及の影響か、一日にあげる量は変わらなくても、愛猫が一度に食べきれる量をこまめにあげているようです。食べムラのある子、食いつきの悪い子は病院受診回数が多いという報告もありますので、日々の食事の様子はしっかり見守りましょう。

獣医師チームから一言
少量のごはんを複数回に分ける食べ方は、ネコちゃんの本来の食生活に近いのでおすすめです。空腹で過ごす時間が短くなると早食いや食べ過ぎ防止につながり、消化もよくなります。
変化②「ごはんの置きっぱなしが減った」
変化①の結果とも関係していますが、「食べ残しがあっても片付ける」飼い主さんの割合が増え、「置きっぱなし」の割合が減っています。こちらも在宅時間が長くなった影響か、きめ細かくごはんを管理され、衛生的で好ましい環境にされている様子が窺えます。
|
食べ終わったら |
食べ残しがあっても |
置きっぱなし |
|
|
2022年 |
25.8% |
32.7% |
41.6% |
|
2021年 |
24.1% |
32.9% |
43.1% |
|
2020年 |
24.0% |
27.8% |
48.2% |

獣医師チームから一言
置きっぱなしのごはんを食べたい時に食べる子も多いですが、特に梅雨から夏にかけてのジメジメした季節はごはんもいたみやすくなります。あまりにも長時間置きっぱなしにすることは避け、お水も定期的に取り替えてあげるようにしましょう。
変化③「水飲み場の複数設置が増えている」
「お水はいくつおいていますか?」という質問では、「1つ」と回答される割合が年々減少(2020年44.2%→21年41.6%→22年39.6%)し、複数設置されている方が増えています。水分補給はしっかりさせてあげることで、膀胱結石や膀胱炎などの尿路系の病気を予防することにつながります。

獣医師チームから一言
ネコちゃんは膀胱炎や尿石症といった泌尿器疾患にかかることが多いので、それを予防するためにも、水分をたくさん摂って膀胱の中を綺麗にしておくことが大切です。お水の数はネコちゃんの頭数+1個が理想と言われていますが、飲水量が少ない子はさらに数を増やしたり、ウェットフードなどから水分を摂れるよう工夫しましょう!
変化④「おやつをあげる人が増えている」
「おやつは1日何回くらいあげますか?」という質問で、「あげていない」を選択した方の割合は年々大幅に減少し(2020年24.7%→21年11.4%→22年9.7%)、9割以上の方がおやつをあげている状況です。おやつの種類はピューレタイプが66.7%(2022年)と1位で、次いでカリカリ系33.8%、3位ささみなどの肉20.4%と続いています。

獣医師チームから一言
おやつは必須アイテムではないですが、ネコちゃんとのコミュニケーションになりますし、お気に入りのおやつがあればご褒美としても使えます。ブラッシングや爪切りなど、ネコちゃんが苦手なお手入れも、おやつを上手に活用することでやりやすくなるかもしれません!
【『ブラッシング&爪切り』ツヤピカにゃんこのお手入れ講座!】
ネコちゃんのお世話に関するにゃんペディア記事はこちらをご覧ください。
□ ブラッシング:猫ちゃんのブラッシング方法
□ シャンプー:今すぐ実践!専門家に聞く上手なシャンプー方法
□ マッサージ:猫ちゃんとの距離が縮まるマッサージの方法
□ 爪とぎ:愛猫ちゃんを爪とぎ上手にする方法
□ 爪切り:自宅で完了!専門家に聞く猫ちゃんの爪切り方法」
変化⑤「おやつの回数と量に気を付ける割合が増えている」
変化④の一方で、「ネコちゃんの体型維持をするうえで最も気を付けている項目を教えてください」という質問では、「おやつの量と回数をコントロールする」と答えた方が増えており、おやつをあげる方が増えるとともに、その量をコントロールして体型維持に努めようとされる意識も高まっているようです。

獣医師チームから一言
喜んでくれるからといって規定量のフード+αでおやつをあげてしまうと、わがままボディまっしぐら。人間と同じで一度増えてしまった体重を落とすのは至難の業なので、おやつのカロリー分はフードを減らして、上手に調節しましょう。
「猫の肥満対策とダイエット法~今日から実践!【獣医師監修】」
生活様式について
変化①「一日に何度も遊んであげる飼い主さんが減っている」
「おもちゃで遊ぶ頻度はどのくらいですか?」という質問では、意外なことに1日2回以上遊んであげる方の割合が減っていました(2回以上遊ぶ方の割合:2020年42.4%→21年41.1%→22年37.9%)。コロナ禍の初めのころ、今まで遊んであげられなかった分、いっぱい遊んであげた飼い主さん。飼い主さんが遊び疲れてしまったのか、ネコちゃんがワンパターンな遊びに飽きてしまったのか…。
一方「数日に1回遊ぶ」と回答された飼い主さんの割合が増えています(2020年18.2%→21年19%→22年22.3%)。コロナ感染防止へのワクチン接種やオフィスでの三密回避の対応など、感染リスク低減によるオフィス勤務回帰の動きもその一因と思われます。

獣医師チームから一言
ネコちゃんにとって遊びは、ただの暇つぶしではありません。遊びを通じて狩猟本能が満たされたり、運動不足も解消されます。遊びが減ってしまうと、物足りなさやストレスを感じて、体調を崩してしまうこともあるかもしれません。毎日ではなくても、時間が確保できる時にはしっかり遊んであげましょう。
変化②「1回に遊ぶ時間は15分以内が増えている」
「おもちゃで遊ぶ時間は1日当たり平均でどれくらいですか?」という質問には、「15分以内」とする方の割合が増えています(2020年60.6%→21年64.2%→22年68.2%)変化①の遊ぶ回数の低下傾向だけでなく、1回あたりの遊びの時間も短くなっています。

獣医師チームから一言
遊びへの集中力はそれほど長くは持たないので、1回あたりの遊びの時間は15分くらいでも問題ないかと思います。ただそれが1日1回だとすると、やはり遊び盛りのネコちゃんにとっては物足りないかも。一緒に遊ぶ時間を確保するのが難しい場合は、ネコちゃんが一人でも動き回って楽しめるよう、知育玩具や自動で動くおもちゃなどを活用するのもおススメです。
「猫との遊びの工夫」に関する記事は、こちらをご覧ください。
□ 誘い方:猫ちゃんも大喜び!猫を遊びに誘うコツ【
□ コツ:猫ちゃんと上手に遊ぶコツ【獣医師解説】
□ 工夫:おうち遊びの工夫♪
□ 機嫌:猫ちゃんの機嫌を損ねない上手な遊び方とは【
□ けりぐるみ:猫が大好きなおもちゃ「けりぐるみ」って何?
変化③「毎日お留守番する子が減っている」
「ネコちゃんはお留守番をすることがありますか?」との質問で「ほとんど毎日」と回答された方の割合が減少しました(2020年45.3%→21年41.8%→22年41.4%)。その分、週に1日程度のお留守番は増え(2020年13.4%→21年18%→22年18%)、「お留守番をするときの平均時間」で「8時間以上」との回答も減りました(2020年32.5%→21年29.6%→22年29.5%)。こちらも在宅勤務の普及がもたらした、ネコちゃんにとってのうれしい変化といえるでしょう。
また留守番中の居場所について質問した結果では、約7割の飼い主さんが「お家の中の自由なところ」とし、2割が「特定のお部屋」、1割が「ケージの中」という結果でしたが、こちらは3年間の変化はありませんでした。
ちなみに、「見守りカメラ」など、お留守番時の様子を確認する機器を設置してる飼い主さんは、緩やかに増えていました(2020年13.3%→21年15.6%→22年17.8%)。愛猫と過ごすおうち時間が増えたことで、かえって留守番させることへの心配や気遣いが増えたことが窺われます。

獣医師チームから一言
ネコちゃんは群れをつくる習性がなく単独で生活していたため、ワンちゃんに比べるとお留守番が得意だと考えられています。でも四六時中飼い主さんにべったりだと、少し姿が見えないだけでも不安になってしまったり、お留守番が出来なくなったりしてしまう可能性も。毎日少しの時間だけでも、一人で過ごす時間をつくってあげると良いかもしれませんね!
※【調査概要】
2021年度:全国のアイペットご契約者さまである犬・猫飼育者 [調査人数]5,873名(犬飼育者4,094名 猫飼育者1,779名) [調査期間]2021年7月10日~7月31日 [調査方法]インターネットによるアンケートを実施
2020年度:全国のアイペットご契約者さまである犬・猫飼育者 [調査人数]6,523名(犬飼育者4,922名 猫飼育者1,601名) [調査期間]2020年3月19日~4月20日 [調査方法]インターネットによるアンケートを実施
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典 」をご利用ください。
例えば、下記のようなさまざまな切り口で、病気やケガを調べることができます。健康な毎日を過ごすため、知識を得ておきましょう。リンクをクリックして調べてみてください。
| 治療 | 症状 |
| □ 再発しやすい | □ 初期は無症状が多い |
| □ 長期の治療が必要 | □ 病気の進行が早い |
| □ 治療期間が短い | □ 後遺症が残ることがある |
| □ 緊急治療が必要 | |
| □ 入院が必要になることが多い | 対象 |
| □ 手術での治療が多い | □ 子猫に多い |
| □ 専門の病院へ紹介されることがある | □ 高齢猫に多い |
| □ 生涯つきあっていく可能性あり | □ 男の子に多い |
| □ 女の子に多い | |
| 予防 | |
| □ 予防できる | うつるか |
| □ ワクチンがある | □ 人にうつる |
| □ 多頭飼育で注意 | |
| 季節 | □ 犬にうつる |
| □ 春・秋にかかりやすい | |
| □ 夏にかかりやすい | 費用 |
| □ 生涯かかる治療費が高額 | |
| 発生頻度 | □ 手術費用が高額 |
| □ かかりやすい病気 | |
| □ めずらしい病気 | 命への影響 |
| □ 命にかかわるリスクが高い |
にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、