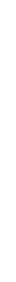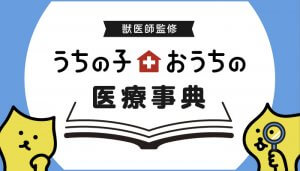飼い猫に、1日でも長く健康で生きていて欲しいと思うのは、愛猫家の共通の願いです。猫を飼うにあたって気をつけたいのが、猫のさまざまな感染症です。
猫の感染症とは?
感染症は、大気、水、土壌、動物(人も含む)などの環境中に存在する病原性の微生物が、体内に侵入することで引き起こされる疾患です。
猫の感染症としては、代表的なものとして「猫ウイルス性鼻気管炎」「猫カリシウイルス感染症」「猫汎白血球減少症(猫伝染性腸炎)」「猫白血病ウイルス感染症:(FeLV)」「猫クラミジア感染症」「猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ):(FIV)」「猫伝染性腹膜炎(FIP)」「トキソプラズマ症」「猫伝染性貧血(ヘモプラズマ症)」などが知られています。
おもな感染経路と予防方法・ワクチンは?
猫ウイルス性鼻気炎
感染猫との直接接触や空気感染。
猫カリシウイルス感染症
感染猫との直接接触や空気感染。
猫伝染性腹膜炎(FIP)
動物の排泄物(とくに便)
猫白血病ウイルス感染症:(FeLV)
ケンカ、グルーミング、食器の共有など。
猫クラミジア感染症
感染猫との直接接触、口や鼻からの感染、空気感染
猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ):(FIV)
猫どうしの接触。詳しくはこちらをご覧下さい。
これらの感症はワクチン接種で予防できる場合もあるようですが、ワクチンによる副作用のリスクも存在しています。

「猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)」のワクチンは存在しますが、ワクチンの抗体が影響し、「猫免疫不全ウイルス」の検査で陽性反応を示すケースがあります。また、生後まもなくの子猫の場合、母猫から母乳によって抗体を受け取ってしまう移行抗体により、検査にて陽性反応が出るパターンもあります。ワクチンを接種する際や、検査を行う時期については獣医に相談することをおすすめします。
現状・ワクチンが存在しない感染症
猫伝染性腹膜炎(FIP)
猫伝染性腹膜炎(FIP)は、それ自体は伝染しないとされていますが、ほとんどの猫が持っている腸コロナウイルスが突然変異したものとされているため、突然変異する前の腸コロナウイルスが排泄物などにより感染します。
トキソプラズマ症
トキソプラズマに感染しているネズミや小鳥などの捕食
猫伝染性貧血
ノミ・ダニが媒介するといわれているヘモプラズマにて感染します。
以上の感染症は予防するワクチンがないため、外に出さないこと、感染の恐れがある猫と隔離をすることがいちばんの予防策となります。
猫の感染症を予防することは、飼い主の責任!
これらの感染症に限らず、一般的に猫が健康的に長生きするためには、定期的なワクチン接種や、感染猫との接触を防ぐことのできる室内飼いをすることが基本となります。外に出たいという猫の欲求を、心を鬼にして退けることが結果的に猫の長寿につながります。
さらに、新しい猫を迎える際には必ず検査をすること、人間を介しての感染を防ぐため、野良猫を触った手で家猫を触らないことも大切です。
また、2006年6月1日に改正・施行された動物愛護法では、「(飼い主は)動物に起因する感染症(人獣共通感染症:ズーノーシス)の予防のために必要な注意を払うこと」とされ、感染症の予防は明確に飼い主の責任となっています。愛猫のわずかな体調変化も見逃さず、速やかにかかりつけの獣医に相談することも大切ですね。
過度なスキンシップは禁物!?、「ペット由来感染症」にもご用心

猫の感染症は人間にうつることはあるのでしょうか? その答えは、残念ながら「YES」です。日本では、動物から人に感染する病気が約50種類ほどあり、そのうちペットから感染する「ペット由来感染症」は約30種類あります。猫による感染症としては、「猫ひっかき病」「トキソプラズマ症」「Q熱」「猫回虫」など8種類が知られています。
近年「ペット由来感染症」は大きな注目を浴びており、その理由としては、ペットの数と種類が増加したことや、室内で飼育することが多くなったこと、濃厚接触する機会が増えたことなどが挙げられます。たとえば「猫回虫」は、口移しや、排泄物に触れることでヒトの体内に取り込まれてしまう、猫への過度な愛情表現が原因となる感染症といえます。
先に記した通り、猫の感染症予防のため室内飼いは必須ではあるものの、日常で気をつけることとして、
・過剰な触れあいを控える
・手洗いをまめに行う
・猫の体と飼育環境を清潔に保つ
・排泄物を速やかかつ適切に処理する
・定期的な駆虫
などを心がけましょう。
猫はかわいい大切な家族ですが、飼うにあたってはしっかりとしたけじめをつけることも重要です。猫の健康的で幸せな生活のためにも、適切な距離感を保つことを心がけ、十分な健康管理を行いたいものです。
*本記事に関連する「にゃんペディア」獣医師監修記事
□ 猫風邪:「猫風邪の症状って?治療法も解説」
□ 猫カリシウイルス:「猫カリシウイルス感染症」
□ 猫ヘルペスウイルス1型感染症:「猫ウイルス性鼻気管炎」
□ 猫エイズ(FIV):「猫エイズに対する正しい理解で、愛猫を幸せに」
□ 猫白血病ウイルス(FeLV):「猫白血病ウイルス(FeLV)感染症とは?治療はどうするの?」
□ 猫伝染性腹膜炎(FIP):「子猫の命を奪う恐ろしい病気、FIP(
□ 猫クラミジア:「猫クラミジア感染症」
□ 猫回虫:「猫の回虫症」
□ ヘモプラズマ:「猫の貧血はどうやって治療する?症状やメカニズムを獣医師が徹底解説!」
□ ワクチン接種:「猫の予防接種(ワクチン)で防げる6つの病気」
□ 多頭飼育:「多頭飼いする前に健康診断!新入り猫の白血病・エイズキャリアの感染は必ずチェック!」
うちの子の長生きのための「健康チェック」に関する獣医師監修記事をご覧ください。
■ 不調のサイン:おうちでできる猫ちゃんの健康チェック方法
■ 自宅で健診:自宅でできる猫の健康チェック
■ 猫の健康チェック:猫の健康状態を確認する方法とは?日常的、
■ 1日の活動量:猫の健康状態をチェック!
■ シニア猫の健康チェック:シニア猫の健康チェック方法とは?
■ 子猫の健康チェック:子猫の健康チェック方法とは?
■ ウンチの見極め:猫のうんちでできる健康チェック
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。