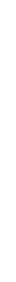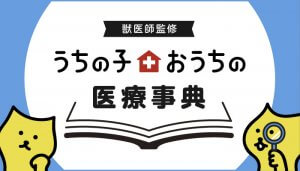猫の平均寿命は年々伸びており、高齢になるまで家族の一員として元気に過ごす一方、高齢になると発症しやすいがんや腎臓病などが病気の中心になりつつあります。実際に、猫の死亡原因の1位は「がん(腫瘍)」で、全体の3分の1以上を占めるといわれています。
腫瘍には良性のものと悪性のものがあり、悪性腫瘍の一部を「がん」といいます。腫瘍は体のどこにでも発生する可能性があり、さまざまな症状を引き起こします。 例えば、皮膚にできる腫瘍はしこりとなり、消化器官であれば下痢や吐き気を、泌尿器官であれば血尿や頻尿などが症状として現れます。さらに進行すると、腫瘍細胞が正常の細胞の栄養をも奪っていくため、食欲が低下したり体重が減少したりするほか、再発や転移といったがん特有の病状で体を蝕んでいくことがあります。 そのため、人の医療と同様に、猫でもがんは早期発見・早期治療がとても大切な病気です。
早期発見・早期治療において、重要な役割を果たすのが「病理検査」です。
病理検査とは、
病気の疑いのある部位の組織などを採取して、細胞の種類や形を観察し、どのような病気なのかを調べる検査
です。
病理検査は、病名を確定する「確定診断」にも用いられ、治療の方針を決定する上でもとても重要な検査です。

病理検査ってどんな検査?
猫のからだは、たくさんの細胞から成り立っています。ある一定の機能や形をもつ細胞が集まって組織を形成し、それらが組み合わさり特有のはたらきを持つのが心臓・肝臓・腎臓などの器官です。
これらの細胞や組織、器官に生じた病変を、肉眼や顕微鏡などを使って観察する検査を病理検査といいます。一般的に、肉眼で組織や臓器に異常が疑われる部分の部位や大きさ、広がり方などを観察します。そして、採取した細胞や組織を特殊な色素などで染色し、顕微鏡で観察します。
これらの結果から、病気の種類(良性腫瘍、悪性腫瘍、炎症など)を判別し、悪性の場合にはその悪性度や転移の可能性の有無などを推測することができます。
身体検査や血液検査、画像診断(X線検査、エコー検査、CT、MRIなど)だけでは診断がつかない場合などに、病理検査は病気の診断や原因の究明において重要な役割を担っています。とくに腫瘍性の病気の場合は、病理検査の結果で確定診断を得ることができ、治療方針の検討や予後の予測に役立ちます。

病理検査の種類
1. 細胞診検査
病気の疑いのある部分から細胞を採取し、スライドガラスと呼ばれるガラスに付着させた細胞に色を付け(染色)、顕微鏡で診断する検査です。
一般的な例として、皮膚や体の表面の触知できるところにしこりができた場合に、それが腫瘍なのかどうか、また腫瘍であればどのような性質なのかをおおまかに判別する目的で行います。
細胞診検査は、しこりや病気の疑いのある部分に細い針を刺し、吸引して細胞を採取します(針吸引)。
針吸引は痛みも少なく、皮下に投与する注射と同じ程度の痛みであるとされていますので、通常は猫に大きな負担をかけずに行うことができます。 麻酔をかけずに行うことのできる検査ですが、猫が動いてしまう場合や攻撃的な場合、危険が伴う場合(顔周りや口周り、足先などの検査)などには鎮静などの処置をしてから針吸引を行う場合もあります。
細胞診検査では、しこりを構成するすべての細胞を採取することはできないので、確定診断には生検や手術などで切除した組織を用いた病理組織検査が必要となります。
また、細胞診はしこり以外にも、血液や尿、腹水、胸水などに含まれる細胞を観察したり、皮膚に症状がある場合にスライドガラスに押し当てて採取した細胞を観察する場合にも用いられます。
細胞診で診断される代表的な病気
・リンパ腫
・組織球腫瘍/組織球性肉腫
・肝リピドーシス
・膿瘍 など
2. 病理組織検査
内視鏡や手術によって摘出された組織を調べる検査です。 組織の採取方法にはいくつかの方法があります。
● パンチ生検
病変の組織の一部を採取して調べる検査を生検(バイオプシー)といいます。
パンチ生検とは、主に皮膚にできた病変を調べるために、皮膚組織を円形に切り取る器具を使用して採取して、観察標本を作成する検査方法です。
皮膚の病変の診断が難しい場合や、治療に対する反応が不十分な場合、また見慣れない皮膚の症状が出ている場合などに行われます。
パンチ生検は犬では局所麻酔で実施することができますが、猫の場合は安全のために鎮静処置を行うことがあります。
パンチ生検で診断される代表的な病気
・天疱瘡
など
● 内視鏡下生検(バイオプシー)
内視鏡下生検は、消化管内視鏡検査(胃カメラ、大腸カメラ)や気管支鏡検査、腹腔鏡検査などを行う際に、病変部をカメラでよく観察し、病変の一部をつまみとって、観察標本を作成する検査方法です。
全身麻酔が必要となります。 組織の一部を採取して検査することから、細胞診よりも多くの情報を得ることができます。
内視鏡下生検で診断される代表的な病気
・呼吸器の病気(鼻腔内腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭炎など)
● 手術で摘出した臓器や組織の病理検査
手術により摘出された臓器や組織を用いて、病理検査を行う方法です。
手術で摘出された臓器や組織は、まず肉眼的に病変が発生した部位や大きさ、広がりなどを調べます。そして、必要な部位の組織から標本を作成し、顕微鏡で観察します。
どのような病変なのか(良性・悪性)、どれくらい進行しているのか、手術で完全に取り切れているのか、追加の治療が必要なのかどうか、悪性の場合にはその悪性度や転移の有無など、治療方針の決定や予後の推測に役立つ重要な情報を得ることができます。
● 病理解剖(剖検)
亡くなられた動物の死因の解明などのために行われます。
生前に行った検査ではわからなかった病気の原因を究明したり、治療の効果があったのかどうかを確認したりすることが主な目的です。
また、稀な病気により命を落とした場合は、これからの動物たちのための貴重な情報提供の機会ともなり、かけがえのない命をつなぐ目的でも行われることがあります。
病理解剖で明らかにされた体の変化は、病気と闘った動物の病態を解明するのに役立つだけでなく、同じような病気で苦しんでいる動物たちの診断や治療のために、大変貴重な情報となります。
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
★にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。

福永 めぐみ
詳細はこちら