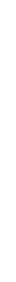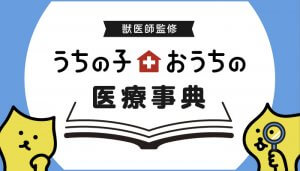高いところにピョンと飛び乗ったり、かと思えばヒラリと飛び降りたり、細い柵の上をヒョイヒョイと事もなく歩いたり……。猫は驚くような運動神経を見せてくれますよね。
でも、運動神経がいいと言えば、犬だってそうです。ただし、得意分野はいろいろと違うよう。
これらの違いは、いったいどうして生まれたのでしょう?実は、進化の過程を見ると、その謎が解けるのです。
犬と猫はもともと同じ祖先だった!

「犬派? 猫派?」なんて言われるように、よく真逆の存在として扱われる犬と猫ですが、実はもともとの祖先は同じだったんです。それはイタチに似た、「ミアキス」と呼ばれる生き物。最初は同じ生き物だったのに、どうしてこんなに違ってしまったんでしょう?
それは、生きるのに選んだ場所のため。平原で暮らすことを選んだものは、のちに犬となり、森で暮らすことを選んだものは、のちに猫となったのです。そして、それぞれの場所で暮らしやすいよう、運動能力が進化していったのです。森の中では、高い木に登ったり、飛び降りるなどの「上下運動」ができなければなりません。現在でも猫は木やキャットタワーに登って活発に上下運動をしますが、犬は高いところには登れませんよね。それは、平原ではそういう能力は必要なかったからです。高いところに登れない犬を上から得意げに見下ろす猫……。そんな光景がよく見られます。
ちなみに猫は、自分の体長の5倍の高さまでジャンプできるといいます。これは、人間にたとえるとビルの3~4階まで一気にジャンプするようなもの。まるでスーパーマンですね。(古い?)
また、草木が生い茂る森の中では、物音を立てると獲物にすぐ気づかれ、巣の中などに逃げられてしまいます。ですから大勢でなく、ひとりで静かに獲物に忍び寄るという狩りの方法が適しています。猫が物音を立てずに歩けるのは、肉球が音を吸収するためと、爪が引っ込められるという特徴からですが、ここにも犬と猫の違いがあります。犬は、爪が引っ込められず出っ放しです。これは、爪がしっかりと出ていたほうがキック力が生まれ、速く長く走れるからです。馬のひづめと同じ原理です。当然、走る音はうるさく、相手にすぐに気づかれてしまいますが、もともと平原ですから、追いかける姿は丸見えです。相手に気づかれるのは百も承知、気づかれて逃げられても、相手が疲れ果てるまでとことん追い詰める、そのためには1匹でなく大勢で追いかけたほうが有利……。犬の狩りは、そのような理屈です。1匹の獲物をしとめるのに10㎞走ることもザラといいます。

猫は、瞬発力はありますが、犬のように長時間は走れません。猫の狩りは、そろりそろりと獲物に忍び寄って、飛びかかるその一瞬で決まります。つまり、猫は短期決戦、犬は持久戦で獲物をしとめるのです。犬と猫の運動能力の違いは、すべてこれに由来します。ですから、どっちのほうが運動神経がいい、と決めることはできません。それぞれに得意分野が違うのです。
ちなみに、チーターは猫科なのに珍しく爪が出っ放しです。これは犬と同じく走って獲物を追いつめる狩りの仕方をするため。静かに忍び寄るよりも、走って獲物をしとめる方向に進化したというわけです。
優れたハンターの技が、現代ではオマヌケに映ることも

このように優れたハンターとしての能力を進化させていった猫ですが、飼い猫として可愛がられるようになった現代では、オマヌケな行動としてうつることもあります。
たとえば、何かに飛びかかろうとするとき、姿勢を低くしてそろりそろりと忍び寄る姿。野生時代の環境では、草が生い茂っていたため、姿勢を低くすれば姿を隠すことができましたが、家の中では丸見えです。でも猫には、野生時代からの根強い習性が残っているので、そうせずにはいられません。「こうすれば見えないニャ」とでも思っているのでしょうか(笑)。
また、獲物に飛びかかる前、おしりをフリフリと振るしぐさ。あれは実は、左右の後ろ足を交互に踏みしめて、飛びかかる角度などを調整しているのですが、これもまた丸見えのため、飼い主には「かわい~♡」しぐさにしか見えません(笑)。このように、現代の飼い猫には「意味のない」習性になってしまったものがあちこちに垣間見えるのも、猫と暮らす醍醐味かもしれません。
猫の歴史に関するにゃんペディア記事
猫と人間との関係の歴史に関する記事もあわせてご覧ください。
□イエネコ:「猫はどこから来たの?イエネコの歴史とルーツ」
□ 世界史:「神か悪魔か。人間に翻弄された猫の歴史とは? <世界編>」
□ 日本史:「猫と日本人。いつから猫は日本にいたの? <日本編>」
□ 源氏物語:「猫が引き起こした大事件 ――『源氏物語』と源氏絵」
□ 古典:「古典『猫の草子』に登場する猫ちゃん」
□ 文学:「【文学】鼠草子絵巻に登場する猫ちゃん 」
□ 物語:「忠義な猫の物語」
□ 進化:「猫が猫になったとき。猫の進化の歴史とは?」
□ 分類:「猫を科学的に「分類」するとどんな位置づけなの?
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。