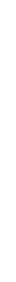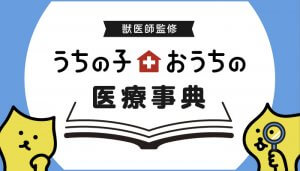子猫のうちは体が十分にできあがっていません。ウイルスなどの病原体から体を守る働きを持つ免疫も、しっかりできあがっていない状態です。そのため、成猫であればなんてことないような病気でも、子猫にとっては危険で重症化してしまうような病気もたくさんあります。
子猫のうちは体が十分にできあがっていません。ウイルスなどの病原体から体を守る働きを持つ免疫も、しっかりできあがっていない状態です。そのため、成猫であればなんてことないような病気でも、子猫にとっては危険で重症化してしまうような病気もたくさんあります。
ここでは子猫の時期に注意すべき病気をご紹介しますので、ぜひ気をつけてあげて下さいね。
猫風邪(ウイルス性鼻気管炎)

ウイルスによって、鼻水や咳、くしゃみなど、人間の風邪と同じような症状を引き起こす病気です。普通の成猫がかかっても、猫風邪だけで亡くなるということはまずありません。
しかし子猫の場合は別。猫風邪にかかって食欲が落ち、栄養が摂取できない期間が続くことで衰弱してしまい、命に関わることも多くあります。「多分猫風邪だから大丈夫。」などと思わず、きちんと動物病院に連れていってあげましょう。
こんな症状が見られたら要注意
□くしゃみや咳を繰り返す
□粘性の高い透明、もしくは黄色の鼻水を出す
□ぐったりしている
□目が開けられない
くしゃみや咳、鼻水などは猫風邪の代表的な症状です。他にも、ぐったりして食欲がないような場合は熱が出ている可能性がありますので、早めにかかりつけの獣医さんに相談して下さい。
また、ウイルスが原因で角膜が炎症を起こしていると、目やにが大量に出たり、目が開けられなくなったりします。この状態が続くと、眼球が腐って失明してしまう場合もあるので、「きっと猫風邪だろう」で済まさずに、必ず動物病院に連れて行ってあげて下さい。
人間の薬を与えるのは絶対にやめて!
猫風邪の治療は、人間と同じように栄養と水分をしっかり補給させた上で、抗生剤などの薬を与えることが一般的です。ただこの時気をつけなければならないのは、絶対に人間の風邪薬を与えてはいけないということ。人間の風邪薬の中には、猫にとって猛毒になる成分が入っている場合もあります。必ず猫専用のお薬を動物病院で処方してもらうようにして下さい。
また、咳や鼻水が出ているからといって、猫風邪だと断定することはできません。もしかしたら他の病気が原因かもしれないので、自分で診断をすることはやめましょう。ひどく衰弱していて病院に連れていけない場合は、電話などで獣医さんに相談して、指示を仰ぐといいでしょう。
予防法
一番効果的なのはワクチン接種です。猫風邪を引き起こすウイルスは全部で4種類ありますが、そのうち3つのウイルスをワクチンで予防することができます。ワクチンは感染を100%防ぐことができるわけではありませんが、ワクチン接種をしておくと、たとえ発症しても重症化を防ぐことができるので、接種しておきましょう。
また、子猫の頃に打ったとしてもワクチンの効果は一生持続するわけではありません。成猫になってからも定期的にワクチン接種を続けてあげて下さいね。
皮膚糸状菌症

皮膚糸状菌症は、皮膚にカビ(真菌)が生えて、顔や耳、しっぽや手足などの皮膚の一部が脱毛する病気です。かゆみが強く出ることがあり、その部分をかきむしってかさぶたができることもあります。皮膚の防御機能が未熟な子猫で発症することが多いとされていますが、毛が長い猫は特にかかりやすいと言われています。
こんな症状が見られたら要注意
□体の一部が脱毛している
□体を掻く頻度が高い
□フケが出ている
□かさぶたができている
この病気は感染している猫と接触することでうつります。多頭飼いをしている場合は、1匹が発症すると他の猫でも発症する可能性が高くなるので、注意が必要です。また、猫だけでなく人にも感染する病気です。もし症状に気づいたら、早めに獣医さんに相談したほうがいいでしょう。
感染してしまったら・・・
よほど体力が落ちていない限り、完治する病気です。ただし治療が完了しても、再度感染してしまう可能性があるので注意が必要です。
猫が使用している食器やおもちゃなどをしっかり洗浄し、屋内の床や壁なども清潔に保ちましょう。湿った環境ではカビが発生しやすいので、湿度管理も大切です。
また多頭飼いの場合は、カビが猫の間で行ったり来たりして、いつまでたっても治らないことがあります。そのような場合は同時に治療する必要がありますので、多頭飼いをしている場合はそのことを獣医さんに伝えておくといいでしょう。
予防法
皮膚糸状菌症は、すでに感染している他の動物との接触によってかかる病気です。そのため、最善の予防策は室内飼いを徹底すること。
ただし、室内飼いの場合にでも発症することがあるので、以下のような場合は注意してい下さいね。
□多頭飼いをしている
□新しい同居猫を迎え入れる
□猫カフェなどで他の猫と接触した
ほかの病気を患っていたり、栄養不良やストレスが多い猫は発症しやすく、症状も重くなりがちですので、日頃の健康管理も重要です。
消化管内寄生虫

子猫に多い病気として消化管内の寄生虫感染があります。代表的な寄生虫を一部、ご紹介しましょう。
□鉤虫
□条虫
□トリコモナス
□コクシジウムなど
寄生虫は宿主の腸などに住みつき、流れてくる栄養素を糧にして生きています。宿主が死んでしまうと、自身も共倒れしてしまうため、基本的には宿主が死なない程度に栄養を吸い取るのです。
そのため健康な猫に感染しても症状が現れないことが多いのですが、免疫力の低い子猫になると話は別。死に至る重い症状を引き起こす可能性があります。また、中には人間に移る寄生虫もいますので、気になることがあったら、早めにかかりつけの獣医さんに相談しましょう。
こんな症状が出てきたら要注意
感染する寄生虫の種類によって症状は異なりますが、共通する症状としては次の通りです。
□下痢
□嘔吐
□腹痛
□腹囲膨満(お腹が膨れること)
□子猫の発育不全
□元気がない
□食べても太らない・痩せる
□毛ヅヤの悪化など
治療法
消化管内寄生虫はそのまま様子をみていても自然治癒することはありません。中には人間に感染するものもあるため適切に治療しましょう。具体的な治療法は感染している寄生虫の種類によって異なります。基本的にはそれぞれの寄生虫に合わせた駆虫薬を定められた期間とタイミングで投与すれば問題なく駆除できます。ただし、トリコモナスは一度感染すると駆除できないことが多いと言われています。
予後
健康な猫に感染しても症状が現れないことも多いのですが、免疫力の低い子猫などに大量感染した場合には、死に至る重い症状を引き起こす可能性もあります。また猫回虫は人にも感染することもあり、要注意です。
予防法
具体的な予防法についてはそれぞれの寄生虫によって異なりますが、共通することは寄生虫は自然発生しないので室内飼育を徹底することで予防できるということです。完全室内飼育であれば新たに感染することはありませんが、ご自宅に来る前の環境次第ではすでに寄生虫に感染しているかもしれません。あくまでも個人的な経験ですが最近は純血種でも寄生虫を持っていることが増えているように思います。腸内の寄生虫感染は便検査を行うことで診断ができます。定期健診やワクチン接種のタイミングで動物病院に便を持参して検便をしてもらうと良いでしょう。
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
★にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。