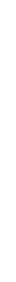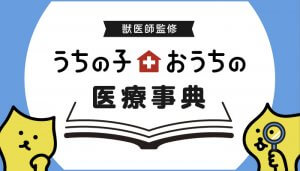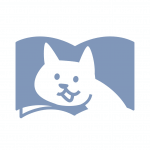猫のしつけは、猫の習性を理解すること
犬のしつけで基本となるのは「ほめたり叱ったり」すること。群れで生活していた犬は飼い主に愛されたいと思い、常に飼い主のことを気にしています。なので、「飼い主にほめられることがしたい、飼い主に叱られたくない」と思うのです。
一方で、単独で生活していた猫は、飼い主を単なる「同居人」のように見ています。なので、猫をほめたり叱ったりしても、なんの意味もないのでしつけにはなりません。そのため、猫にしつけをするのではなく、
猫の習性を理解し、猫に合わせて猫と人間が気持ちよく暮らすための解決策を見つける
ことが、ポイントになります。
爪とぎのしつけ
爪とぎは猫の本能なので、無理にやめさせようとしても猫のストレスがたまるだけです。爪とぎ自体をやめさせようとするのではなく、猫の習性に合わせた環境づくりをする必要がなります。
猫が爪とぎをしやすい場所に、「爪とぎ器」を用意する
まずは、爪とぎの場所を確保して、他の家具や壁に爪とぎをさせないことが重要です。爪とぎ器は以下ポイントに注意しながら設置するようにしましょう。
■爪がひっかかりやすい段ボールや木材などの素材を使う
■猫の目につく目立つところに、必要に応じて複数個設置する
■猫は起きてすぐに爪を研ぐ習性があるので、猫が寝ている場所の近くが理想
家具や壁で爪を研いだら「現行犯逮捕」
もし、ソファやテーブルなどでツメを研いでいたら、すぐに爪とぎ器の場所に連れていきましょう。家具や壁でツメを研ぐことがクセにならないよう、特に子猫のうちは細心の注意が必要です。
猫ちゃんを爪とぎ上手にするためには、「愛猫ちゃんを爪とぎ上手にする方法」もあわせてご確認ください。
トイレのしつけ
トイレのしつけの考え方も爪とぎと同じ。猫ちゃんがしたい場所にトイレを置く、くらいの心構えが必要です。具体的なしつけのポイントは以下の通り。
トイレのしつけは生後3~4週間後
トイレのしつけは初めが肝心。生後一カ月弱経って、固形の食事をするようになったら、トイレのしつけを始めましょう。猫がウロウロして落ち着かなくなったら、トイレの合図なのでトイレに連れて行きましょう。次第にトイレに行くことが習慣になっていきます。
「粗相」をしたらすぐに痕跡を消す
万一、トイレ以外の場所でウンチやおしっこをしてしまった場合は、すぐに掃除して念入りに臭いを消しましょう。猫は自分の臭いがついている場所でなんども排泄しようとする習性があるので要注意です。
トイレは静かなところで、常に清潔に!
猫がトイレを使いたがらない場合は、トイレの場所が気に入らなかったり、トイレが汚れたりしていることがあります。猫がトイレを使ってくれるよう場所を変えてみたり、こまめな掃除を心がけるようにしましょう。
猫ちゃんに気に入ってもらうトイレの作り方については、「猫ちゃんが喜ぶ!快適なトイレの作り方」の記事も読んでみてください。
コマンドトレーニング
次に、「ネコちゃんに行儀を教える」というより、飼い主さんとの信頼関係を作り、上手にコミュニケーションをとれるようにする、オススメの方法、“コマンドトレーニング”をご紹介します!
〈 名前を呼んだら来る猫に 〉
〈 お手編 〉
〈 ハウス編 〉
猫ちゃんは人間の思い通りに行動してはくれません。それがまた猫ちゃんの魅力。猫ちゃんが気に入ってくれる環境をつくることで、飼い主さんにとっても暮らしやすいおうちになっていくはずです。楽しみながら猫ちゃんお気に入りのポイントを見つけてあげてくださいね。
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
★にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。