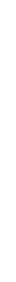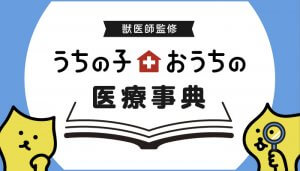野生で生きてきた猫は、生存するための戦略として、他の動物との競合を避け、人間の世界で生活するという道を選びました。人間の世界で生きていくためには、人間と仲良くする必要があります。今では動物病院に来ても、私にスリスリ顔をこすりつけたり、ゴロゴロと喉を鳴らしてくれる猫もいますが、これは1万年前の猫では考えられないことでした。長い年月をかけて、猫は人を恐れないようになったのです。とはいえ、中には警戒心が強く、なかなか心を開いてくれない猫もいます。この性格の差は、一体なんなのでしょうか?
フレンドリーな猫と警戒心の強い猫の違い
猫が人間に対してフレンドリーになるかどうかは、個々の資質と幼少期の過ごし方が大切だと考えられています。フレンドリーな猫の資質を持っているかどうかは、母猫よりも父猫の遺伝子の影響が大きいと考えられていますが、通常その資質まで見極めることはできません。なのでここでは、フレンドリーな猫に育てるための幼少期の過ごし方についてご紹介します。

猫が社会に慣れるための期間
猫が他の動物とのコミュニケーションを学ぶ期間を「社会化期」と呼びます。猫の社会化期は生後3〜9週齢の間。この時期に
他の動物と適切な接点をもたないと、生涯に渡ってコミュニケーションが苦手な猫に
なってしまいます。反対にこの時期から一緒に過ごしている相手であれば、本来なら獲物であるはずの小鳥やネズミや、さらには恐れる対象であるはずの大型犬に対しても攻撃性を示さなくなることがあります。動画サイトで異種の動物と仲良くしている猫が人気ですが、これは社会化期に異種の動物との生活に順応したためにできることなのです。この
3〜9週齢の社会化期の間に人間と一緒に生活することで、人間に対しても社交的な猫に育ちやすい
と言われています。2週齢から人間の手に触れていた子猫は、より人間に慣れやすく、さらに一人の人間としか交流がない猫よりも、
多くの人に触れられた方が社交的な猫になる
という研究結果も報告されています。つまり、社交的な猫に育てるためには、この時期にたくさんの人と会わせることが大切なのです。オフィスや動物病院などで小さい頃から可愛がられた猫は、やはり社交的な子が多いと思います。
社会化期の注意点
猫に嫌なイメージを与えないで
ただし、単純に沢山の人を家に呼べば良いというわけではありません。
猫の扱いを知らない人に乱暴に扱われると、それはマイナスの印象として猫の記憶に強く残り、逆に人を避ける
ようになる可能性も十分にあるからです。特に小学生以下の子供は要注意です。猫に合わせる前に、まずは猫がどんな生き物なのか、どんな風に接したら良いのかを教えてあげてからにしましょう。おもちゃを使った猫との遊び方、猫が気持ちよいと感じる撫で方や抱っこの仕方、寝ている時は無理に起こさないなど、基本的なことからきちんと教えてあげてください。
全ての猫が社交的になるわけではない
社会化期に色々な人間と適切に接点を持ったからといって、絶対に社交的な猫に育つわけではありません。1996年に発表された論文には、
15%の猫は社会化がうまくいかない
と書かれています。これは生まれ持った性格・資質の問題なので、無理に矯正することはできません。人間ひとりひとりに個性があるのと同様に、猫にも色々な性格の子がいて、甘えん坊な子もいれば、ベタベタするのが苦手な子もいるのです。無理やり人に慣れさせようとすると、恐怖心を植え付けてしまったり、飼い主さんとの関係性を悪化させてしまう可能性もあります。猫の性格を尊重して、シャイな子の場合はそれ以上猫の頭数を増やさない、来客時は奥に隠してあげるなどして、その子が幸せに暮らせるような環境を整えてあげてください。
社会化期をうまく過ごすために
純血種の場合
現在は動物愛護法により、原則として生後8週齢未満での販売は禁止されているため、ブリーダーやペットショップから購入した猫は、既に社会化期が終わりつつあります。そうなると、その猫がどれだけ人に慣れるかは、ブリーダーの飼育環境や親猫の資質次第、ということになります。とはいえ人に育てられた猫は野良の猫よりも社会化期が長いと言われているので、9週齢以降も様々な経験を積ませることは大事だと思います。また、子猫に適切な社会化期を送らせてくれている良質なブリーダーを見つけることができればいいのですが、なかなか簡単なことではありません。友人の猫が非常にフレンドリーな子であれば、そのブリーダーさんを紹介してもらうと良いでしょう。
保護猫の場合
授乳期の猫は通常兄弟も一緒にいるので、1匹だけで保護されることは少ないと思います。里親を探す場合は、9週齢までは兄弟猫と離さず、いろんな人と遊ばせてあげるといいでしょう。この時期にいろんな人や猫と触れ合うことで、知らない人とも仲良くできる会う練習になります。ちなみに、ノラ猫は人に慣れているほど地域で可愛がれ、食事にありつけるので、ノラあがりの猫はフレンドリーな猫が多いようです。しかし、幼少期に人からいじめられたりした経験があると生涯を通して人に恐怖を抱いてしまい、そうすると成猫になっても人に心を打ち明けるのは難しいことがあります。
人間に対して警戒心が強い子は、そういったところがまた可愛かったりもするのですが、体調を崩したときに動物病院に連れていくのが少し大変です。病院へ行くことへのストレスから、余計に体調を崩す場合もあるからです。その子の性格を尊重しつつ、できる範囲で人間に慣らしてあげる練習はしてみてくださいね。
【参考文献】FelineBehaviorAGuideforVeterinarians.SecondEditionBeaver,BonnieV.
★「うちの子」の長生きのために、気になるキーワードや、症状や病名で調べることができる、獣医師監修のペットのためのオンライン医療辞典「うちの子おうちの医療事典」をご利用ください。
にゃんペディア編集部からのメールマガジン配信中!
「にゃんペディア編集部」では、愛猫との暮らしに役立つお勧め記事や、アイペット損保からの最新情報を、にゃんペディア編集部からのメールマガジン(月1回第3木曜日夕方配信予定)でお知らせしています。ご希望の方はこちらからご登録ください。